SUMMARY地籍調査の概要
定義と説明
地籍調査とは、国土調査法に基づく土地に関する調査であり、千葉市が一筆毎の土地について「所有者」「地番」「地目」を確認するとともに、境界の位置や面積を測量し、地籍図および地籍簿を作成する作業です。ここでいう「地籍」とは、土地の所有者、地番、地目(宅地・畑などの土地の用途区分)を記録したもので、「土地の戸籍」にあたるものです。また、地籍調査は行政が実施する事業のため、測量などにかかる費用については土地所有者の皆さまの負担はありません。
PURPOSE &
SIGNIFICANCE地籍調査の目的と意義
目的
法務局が管理する公図は明治時代に作成されたものも多く、土地の形状が公図と現状で異なっている場合があります。また、土地の面積が一定程度明確化されている都市部においても測量技術が古かったり、境界点の座標値が管理されていなかったりする等、登記簿に記載されている面積と実際の面積が異なっている場合もあります。さらに、登記簿に記載された情報が更新されず、土地の利用状況や所有者の住所が古いままになっているケースも少なくありません。そこで、土地の最も基本的な情報である地籍の正確な情報を明らかにすることを目的に、地籍調査を実施します。
意義
■ 災害時の迅速な復旧
■ 都市計画推進への貢献
■ 境界トラブルの防止
■ 財産権の明確化(登記との関係)
PURPOSE &
SIGNIFICANCE地籍調査の効果
効果
地籍調査を実施することで、道路や隣接する土地との境界が明確になり、境界をめぐるトラブルの未然防止につながります。また、地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)に基づいて、これまで法務局に備え付けられていた公図及び登記簿が修正されることから、登記簿上の面積と実際の土地面積が一致し、土地取引の円滑化にも貢献します。さらに、境界点が座標値で管理されることから、災害時に境界標が失われても正確に復元が可能となり、復旧工事を迅速に進めることができます。こうした土地所有者のさまのメリットに加えて、地籍調査の成果をまちづくりの基礎資料として活用することで、都市計画やインフラ整備などの各種事業を円滑かつ迅速に推進することが可能となります。
■ 土地の境界をめぐるトラブルの未然防止
■ 土地取引の円滑化(不動産取引における信頼性向上)
■ 災害時の迅速な復旧
■ まちづくりの推進
FLOW地籍調査の具体的な流れ
千葉市の地籍調査は、ひとつの地籍調査区域を概ね3年かけて実施します。1年目・2年目・3年目の調査の流れは以下のとおりです。なお、一筆地調査(現地立会い)・境界標設置・成果の閲覧については、土地所有者さまの積極的なご参加をお願いします。また、現況測量・復元測量・一筆地調査(現地立会い)・境界標設置・一筆地測量においては、土地所有者さま等の許可を頂いてから敷地内へ立ち入らせて頂くことを予定していますので、ご理解とご協力をお願いします。
1年目の工程
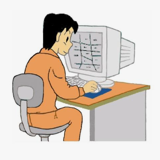
①地権者調査
地籍調査対象区域の土地について、公図及び土地登記簿を取得し、地番、所有者、地目、地積等を調査するとともに、備え付けの地積測量図を取得し現況測量の基とします。
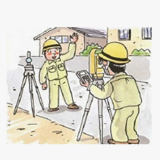
②細部図根測量
各種測量を実施するための基礎となる図根点(基準点)を主に道路に設置します。
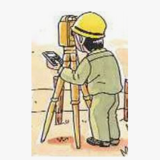
③現況測量
個々の土地について現地の状況を把握するため、既存の境界杭や境界と見なせる塀などの位置を調査・測量し、現況測量図を作成します。
2年目の工程

①復元案作成
現況測量図や地積測量図等を用いて、市が法務局などと協議しながら筆界の復元案を作成します。※ 筆界とは土地と土地の境界線のことです。

②復元測量
筆界の復元案に基づいて境界点の位置を現地にペイント等で表示します。

③現地立会
土地所有者さまに復元測量により復元した境界点を確認していただき、境界点の同意・不同意について意向を伺います。

④境界標設置
現地立会いにより同意が得られた境界点に「千葉市地籍調査金属標」等を設置します。
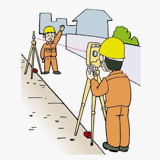
⑤一筆地測量
確認のため、境界点の同意を得た筆を対象に、土地の境界(筆界)の位置を測量します。
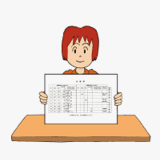
⑥地籍図及び地籍簿作成
一筆地測量を基に、各筆の土地面積を計算するとともに、正確な地籍図原図と地籍簿案を作成します。

⑦成果の閲覧
地籍図原図と地籍簿案を閲覧に供し、境界立会の結果が地籍図及び地籍簿案にどのように反映したのか土地所有者の皆様に確認していただく機会になります。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
3年目の工程

①法務局送付
閲覧後の「地籍図」と「地籍簿」は、千葉県の認証及び国の承認を受けた後、その写しを市が法務局に送付します。法務局において地籍簿に基づき、登記簿が書き換えられ、公図にかわり地籍図が備え付けられます。
地籍調査事業では、現況測量、復元測量、境界立会、境界標の設置、一筆地測量などの工程において、敷地内へ立ち入らせていただく機会がございます。具体的には、1年目に1回、2年目に4回程度、事前にご案内のうえ、土地所有者様の許可をいただいてから作業を実施する予定です。調査の円滑な実施のため、皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ROLE地籍調査における関係機関の役割
地籍調査は、市町村が発注し、受託法人が調査・測量作業を実施します。その後、成果物は複数の検査や認証・承認を経て、最終的に登記所(法務局)へ送付され、登記簿や地図情報に反映されます。また、地籍調査の成果は、都市計画や災害対策など、市町村による多目的利活用にも活用されます。この調査の流れにおいて、関係機関が担う主な役割は以下のとおりです。
関係者とその役割
| 千葉市の役割(調査主体) | ・地籍調査計画の策定・実施管理 ・土地所有者への説明・周知 ・受託法人の監督 ・委託者検査(成果検査) |
|---|---|
| 登記所(法務局)の役割 | ・地籍調査区域の事前説明・調整 ・公図および登記簿情報の提供 ・復元案の協議 ・地籍図および地籍簿の受領・保管(登記記録へ反映) |
| 千葉県の役割 | ・地籍調査に関する指導・推進説明 ・成果物の認証(県による検査) |
| 国土交通省の役割 | ・地籍調査にかかる予算措置 ・成果物(地籍図等)の最終承認 |
| 土地所有者の皆さまの役割(協力者) | ・現況調査へのご協力 ・現況測量・復元測量へのご協力 ・境界立会・確認作業へのご協力 ・境界標設置の了承 ・一筆地測量(点検)のご協力 ・調査成果(地籍簿・地籍図)の閲覧確認 |
| 千葉市地籍調査協会(当協会)の役割(実施者) | ・一筆地調査(所有者・利用状況の確認) ・細部図根測量(基準点の設定) ・現況調査・現況測量 ・復元測量(境界案に基づく測量) ・一筆地測量(点検測量) ・地籍簿・地籍図の作成 ・閲覧対応(成果の確認手続) ・自主検査(受託法人としての内部成果検査) |
市民が関与する場面と必要な手続き
地籍調査では、土地所有者の皆さまのご協力が必要な場面がいくつかございます。
調査の円滑な実施と、正確な成果の作成のために、以下のような場面での立会いやご確認の手続きをお願いしております。該当する区域の皆さまには、事前に書面やお電話等でご案内いたしますので、日程調整や必要書類のご準備をお願いいたします。
| 立会や協力の重要性 | 地籍調査は、土地の境界や面積を正確に明らかにすることを目的とした公的な調査です。この調査では、所有者ご本人またはご家族の方に、以下の場面でのご立会いや確認にご協力いただく必要があります。 |
|---|---|
| ご協力いただく主な場面 | 現況調査・現況測量 現地の境界標の設置状況や利用状況、土地の形状を地積測量図や公図と比較しながら確認するため敷地内に立ち入らせていただくことがあります。 復元測量復元検討図に基づいて境界点を復元する際立ち入らせていただきます。 境界立会復元した境界点(境界線)について立会って確認していただきます。 境界標設置確認して頂いた境界位置に境界杭を設置する際に立ち入らせていただきます。 一筆地測量設置した境界標にについて最終的な点検測量として実施するために立ち入らせていただきます。 成果の閲覧千葉市の庁舎で、作成した地籍調査の成果(地籍簿・地籍図)を閲覧に供し、確認をしていただく機会を設けます。 |
| 必要書類や連絡先 | ご立会いや確認の際に、以下の書類や情報をご準備いただくと手続きが円滑に進みます。 |
| ご準備いただくもの(該当する方のみ) | ・ご本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど) ・委任状(代理人が立会う場合) ・所有者不在時の連絡先情報(例:ご家族、管理会社など) |
| お問合せ・ご連絡先 | 一般社団法人 千葉市地籍調査協会 ・所在地:〒260-0013 千葉市中央区中央3丁目12番3号 KJS千葉中央ビル ・電話番号:043-331-3638 ・メール:office@chibashi-chiseki.or.jp ・受付時間:平日 9:00~17:00(土日祝を除く) |

